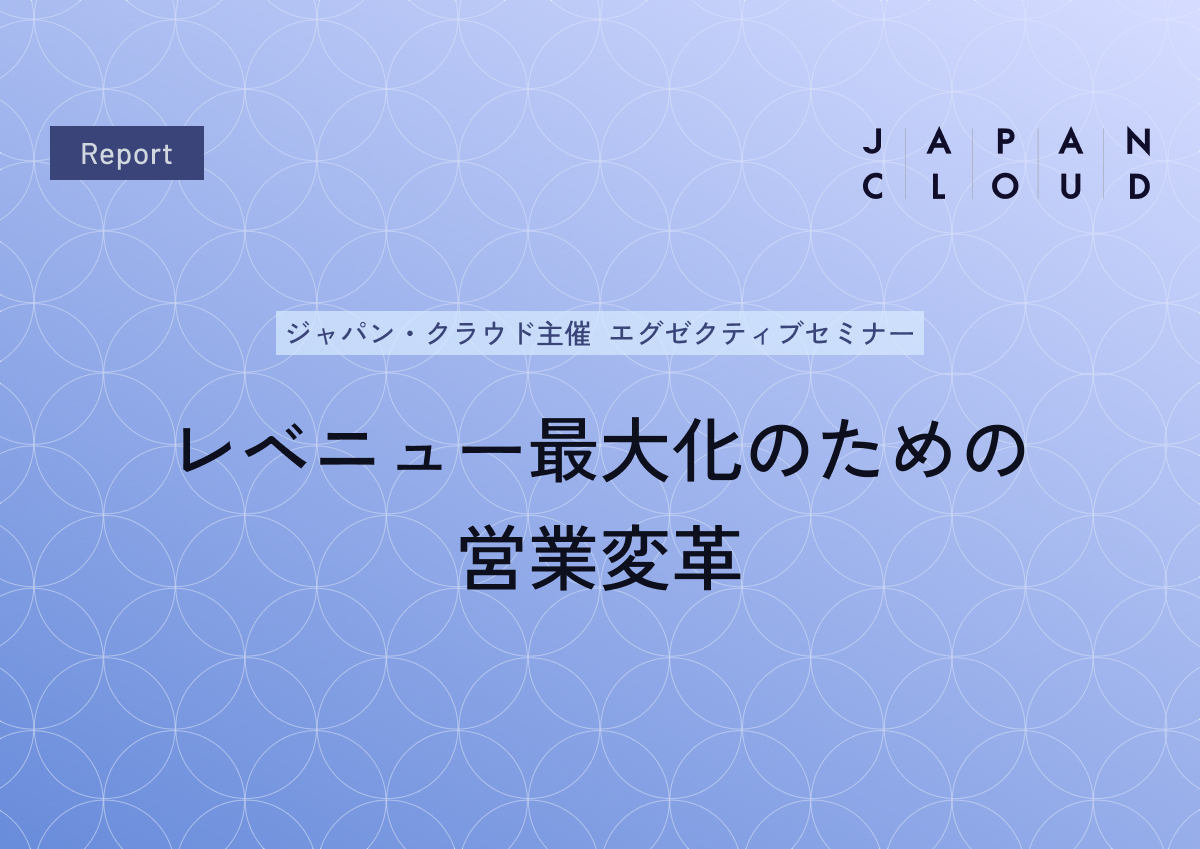生成AI時代に求められるのは「変革を牽引する視点」三井住友FG、三菱マテリアル、富士通のITリーダーが激論を交わす ~「CIOカンファレンス2025」開催レポート~
![]()
Japan Cloud

本記事は、2025年7月10日に JBpress「Japan Innovation Review」に掲載された広告記事と同内容です。
▶︎オリジナル記事はこちら
2025年5月22日(木)、東京港区の赤坂インターシティコンファレンスで「CIOカンファレンス2025」(主催:ジャパン・クラウド・コンサルティング)が開催された。テーマは「生成AIで変革する経営戦略と企業組織」。最新の技術動向や企業戦略に関する情報提供と、参加者間の交流を目的として開催されたもので、会場には生成AIが企業経営にもたらすインパクトへの関心が高いリーダー層が集った。経済産業省「DXレポート」の実質的な著者である和泉 憲明氏や、米モルガン・スタンレーにて生成AIや次世代フィンテック領域の数多くの取引をリードしてきたShaan Tehal氏の他、三井住友フィナンシャルグループ、三菱マテリアル、富士通といった業界を代表する企業から3名のITリーダーが登壇。本記事では、高い注目を集めた本イベントの要点を紐解いていく。
開会の挨拶に立ったのはジャパン・クラウド 代表取締役社長の福田 康隆氏だ。

生成AIにより作成された本人のアバターに紹介される形で登壇した福田氏は、「生成AIはIT分野に閉じたものではなく、人間の役割を根本的に変えるもの」と話し、これまで18社の海外SaaS日本進出支援の経験で得たJAPAN CLOUDとしての知見を日本企業に共有したいとしてカンファレンスの開幕を宣言した。

基調講演を行ったのは、AIST SolutionsのVice CTOで、元経済産業省 商務情報制作局 情報経済課 アーキテクチャ戦略企画 室長の和泉憲明氏だ。経済産業省が2018年に公表した「DXレポート」の実質的な著者のひとりである和泉氏の演題は『生成AI時代の経営戦略と企業成長――「2025年の崖」をレバレッジに変えるために』である。
技術革新だけでは馬車は自動車に置き換わらなかった
「2025年の崖」とは、企業の競争力や日本経済全体の持続可能性に関わる構造的な課題を、ITシステムの老朽化やDXの遅れによる経済的損失に照らし合わせ、2025年以降に最大で年間12兆円も生じるという試算により指摘した問題だ。和泉氏は、2025年度に入った今も、課題は根本的には解決しておらず先送りされているだけだと指摘する。
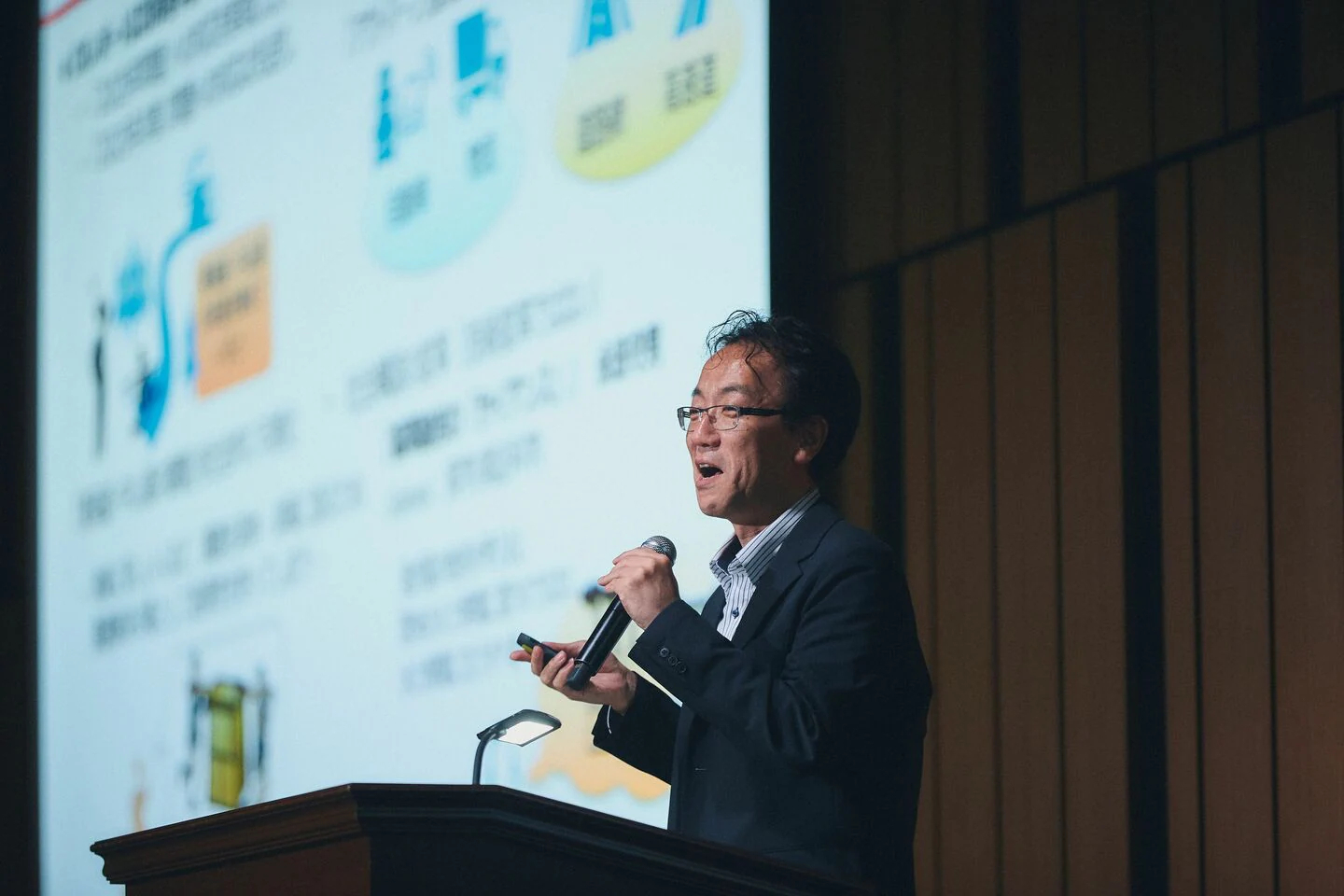
「この問題の本質を議論する前に、ビジネスの現場で起きていることは、言わば『東海道を走っている飛脚のわらじが脱げかけて前に進めなくなっている』といったような現場で発生する足元の課題についての議論でした。ところがそうした陳情を受けた経営者や政策セクターは『では、東海道を舗装しましょう』というような、目先の対応ばかり。これでは見当はずれです。本来は、例えばドイツでの取り組みを規範とすると、実質的に速度無制限の高速道路である新たなインフラ「アウトバーン」を政府が整備し、そのインフラの上での技術競争により民間は企業競争力を向上させると言った様な、全体的なアーキテクチャの策定に取り組むべきです。
また、自動運転などで注目され続けている自動車分野の技術革新については、幌馬車がT型フォードに置き換わった過去に学ぶべきだと言及した。
「利用者にとっては、幌馬車かT型フォードかという違いはさほど影響を与えません。自動車への移行を後押ししたのは、むしろその周囲の人々でした。T型フォードは馬の様に路上を汚すことも、突発的に制御を失うこともありません。つまり、変化の本質は新技術そのものではなく、「より清潔で安全な手段を社会が指示した」という意識の変化にあったのです」
続けて和泉氏は、サンフランシスコ市街で深夜に目撃したという、ロボットタクシー・ウェイモ(グーグルの親会社アルファベットが開発するドライバー不要の自動運転モビリティ)の利用シーンを紹介した。
「女性がひとりでウェイモを呼んで帰宅するのを見ました。しかも二度です。タクシーやウーバーを使ってドライバーと一対一になることのリスクと、自動運転モビリティのリスクを秤にかけ、後者を選んでいるのです。そうしてウェイモが使われれば使われるほど、ウェイモは学習し賢くもなります。日本で『自動運転の性能はまだまだ』と言っている人たちは、彼女たちのようなユーザーを想定していないのでしょう。そうした人たちに、ITについて正しい投資ができるとは思えません」
和泉氏はかつて、スタンフォード大学名誉教授でAI分野の権威であるエドワード・ファイゲンバウム氏にインタビューした際に、「これから必要なのはHowの改善ではなくWhatを定めることだ」と聞いたという。それを受け、「日本企業はHowの改善を得意としてきましたが、すでに生成AIにWhatを与えればHowが返ってくる時代です。これからのビジネスモデルは、それを前提にすべきです」と投げかけた。
人間の2つの根源的な欲望「成長」と「利便性」を満たすAIが伸びる
続いては、米モルガン・スタンレーで生成AIや次世代フィンテック領域で数多くの取引をリードしてきたShaan Tehal氏とジャパン・クラウドの共同創業者兼CEOのAruna Basnayake氏が、『生成AIが経営にもたらす構造変化 米国トップアナリストが語る生成AIトレンドとインパクト』と題して、グローバルにおけるAIを始めとしたテクノロジーの最先端を紹介した。

Tehal氏は「米国では生成AIの活用が『実験段階』から『本番運用』へと新たなフェーズに入り、単なるチャットボットはなく『業務の一部』として組み込まれ始めている」と指摘。その進化はあらゆる領域で多くのユーザーが実感しているはずだとした。
「たとえば会計ソフト企業では、税務申告支援にAIエージェントを導入し従来のナビゲーション業務を代替、中古車オンラインシステム企業では、膨大な車両データをもとに販促文をAIが自動生成し、生産性と顧客体験を向上させている。創造性を要しない業務はすでにAIに置き換わりつつあり、AIは『新しい労働力』として業務設計そのものを変える。今、問われているのは「どう使うか」ではなく「どう組み込むか」という論点だ」と述べた。

Basnayake氏は「人間には2つの根源的な欲望があります。まずは成長で、これまでの日本企業はこの成長という側面で大きな役割を果たしてきました。もう一つの欲望は利便性、特にラストワンマイルの「煩わしい」を取り除く利便性です。人間は誰しも楽をしたいものです。多くの人はここに価値を見出すとお金を支払います。そして今、発展しているのはこの部分で生成AIを使って新たな価値を提供できている企業です」と語った。
三井住友フィナンシャルグループ、三菱マテリアル、富士通ではどのように生成AIを活用しているのか
『日本の大企業の生成AI最前線 理想と現実の間に』と題し、約1時間にわたって行われたパネルディスカッションには、Tehal氏のほか、日本を代表する企業の3人のITリーダーも加わって議論を繰り広げた。進行役はジャパン・クラウドの福田氏が務めた。

まず社内での生成AIの活用実態について、三井住友フィナンシャルグループ 執行役専務グループ CDIOの磯和 啓雄氏は「2023年7月に、全行員が利用できる生成AIをリリースしましたが、利用実態はというと翻訳やメールの返信に留まっていました。そこで、生成AI活用の取り組みを加速させるために、AIの投資枠を設定したところ、社内から半年で30件ほど案件が出てくるようになりました。先日ローンチした各種金融サービスをまとめて管理できるサービスOliveの法人版であるTrunkにも、生成AIを活用しています」と述べた。

三菱マテリアルのCIO(最高情報責任者)でシステム戦略部長の板野 則弘氏は「第2次AIブームの頃から、生産技術には当時の最新技術を導入してきましたが、生成AIについては全事業部門で、翻訳や議事録作成、検索に利用しており、使いこなしている部門や業務とそうでないものに効率の差が生じ始めています」とした。

富士通 執行役員専務 エンタープライズ事業CEOの福田譲氏は「富士通の約4割の社員が毎日生成AIを使っていて、1日あたりでは約30万回」と現状を語った後、カスタマーサポートについても「毎日、万単位で問い合わせがありますが、そのうちの3分の1ほどは生成AIが自動的に対応しています」と明かした。

テーマが「投資対効果とその測定」に移ると、3年で500億円規模の投資を進めている三井住友フィナンシャルグループの磯和氏は「実は、予想もできないところに効果が出ると思って自信を持って取り組んでいます」と胸を張った。同社ではコールセンターにAIを導入しているが、当初は低かった精度も使用頻度に比例して高まっていき「当初の想定である業務効率化以外に、退職率が激減するという思わぬ副次的効果を発揮しました」というエピソードを披露した。
また富士通の福田氏は「ROIを考える上で、もっともわかりやすいのは、生成AIによって人は人間らしい仕事に集中し、その結果、何人を削減できるかという視点でしょう。削減できる人件費をデジタル予算に変えて企業を筋肉質な体質にしていくことがテクノロジーリーダーに求められていることではないかと思います」とし、Tehal氏は「海外では生成AI導入によるROIは想定よりも軒並み高くなっています」と現状をレポートした。
三菱マテリアルの板野氏は「効果を議論するうえでは、生成AIが消費するエネルギーにも着目し、社会全体での投資対効果を考えるべきではないでしょうか」と視座を示した。
生成AIと人類はどのように共存し働くのか
最後に、これからの生成AIの活用によって起こると予想することや期待について、それぞれが述べた。
「最もインパクトが大きな変化は、組織の変革でしょう。今の組織は、人間の認知能力に基づいて構成されています。顔と名前が一致するのは100人までだからこの部署は100人までです、それ以上は別組織ですという対応をしてきた結果が今の組織です。しかし、AIの認知限界は人間を遥かに超えます。AIを活用すれば一人の上司が1万人の部下をマネジメントすることもできるようになりますし、すでにAIに合わせた形に組織を変革するタイミングが来ているような気がします。そしてその変革をいち早く達成した組織が優位な立場に立つのではないかと思います。個社ごとに戦う時代ももう終わりを告げるのかもしれません。」(磯和氏)
「私たち素材メーカーの歴史は効率化の歴史でもありましたが、しかし1990年代にパソコンが1人1台配られて、どうなったでしょうか。仕事が楽になるはずが、もっと忙しくなりました。今後も、空いた時間を何に使うのか、ウェルビーイングという答えももっと創造的な仕事という答えもあるでしょう。そこで忘れてはならないのは、テクノロジーは人を幸せにするものであるということです。特に日本には、海外と比べても新しいものを創造することができる人が大勢います。生成AIなどの新しいテクノロジーは徹底的に、人を活躍させる方向に使うべきだと考えます。今後も企業は、その実現の場であるべきではないでしょうか。」(板野氏)
「フォードが顧客に『何がほしいか』と尋ねていたら、発明されていたのは自動車ではなくもっと速い馬車であっただろうという逸話があります。今、テクノロジーリーダーに求められるのはこのフォードの姿勢であり、より速い馬車を追求するのではなく自動車へ舵を切ること、新しいトレンドを作っていくことです。フォロワーシップからリーダシップへ、自分たちで仮説を立て、周りを巻き込んで、もっと前面に立って進んでいくことが求められていると思います。」(福田譲氏)
白熱したパネルディスカッションは約1時間続き、最後にTehal氏が「テクノロジーは 限界を超えるところまで活用すると伸び代が見えてくるので使い倒すことが大事。また単なる改善に留まらずプロセス自体を見直してみることが今求められている。」と締めくくると、会場からは大きな拍手が沸き起こった。

いずれのテーマも参加者の変革への意識を高める内容で、客席では熱心にメモを取る姿が見られた。国内外のトップリーダーの言葉は、多くの刺激となったことは間違いがない。その余韻は、パネルディスカッションの後に設けられた懇親会/ネットワーキングの場にも残っていた。